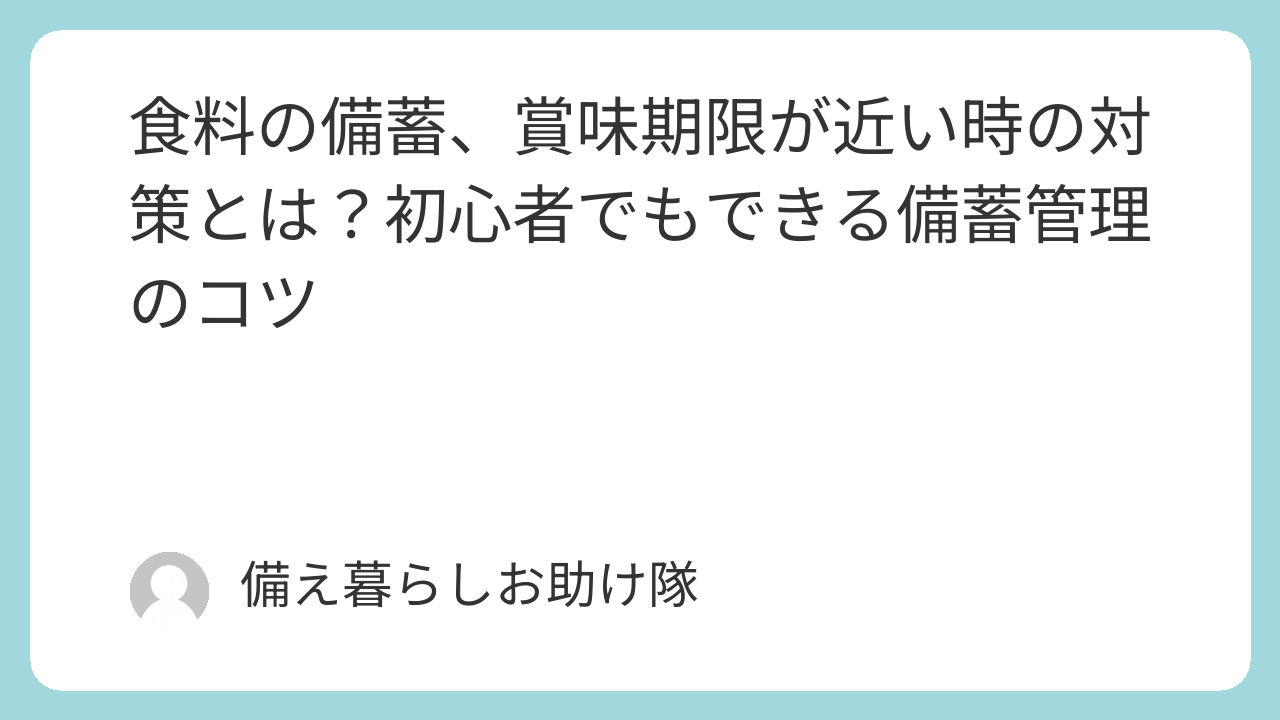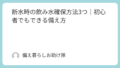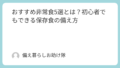なぜこの備えが必要なのか?
地震や台風、豪雨など、いつどこで起こるかわからない災害に備えて「食料の備蓄」をしている家庭は年々増えています。
しかし、いざ備えを始めてみると「賞味期限が近づいてしまった」「気づいたら期限切れ」というケースも多く、管理に悩む人も少なくありません。
実はちょっとした工夫で、無理なく備蓄食品を活用・循環させることができるのです。
食料備蓄とは?|初心者向けにやさしく解説

食料の備蓄とは、災害や流通停止など非常時に備えて、自宅に一定量の食べ物を保管しておくことを指します。
政府は「最低3日分、できれば1週間分」の備蓄を推奨しており、乾パン、レトルト食品、缶詰などが代表的です。
しかし、これらには賞味期限があるため、定期的に入れ替える必要があります。
実は知らない人も多いのですが、「ローリングストック法」を使えば、期限切れのリスクを大幅に減らせます。
備蓄は特別なことではなく、普段の食生活の一部として管理することがカギです。
実践パート|どうやって始める?どう管理する?

備蓄品リストを作成する
まずは家庭で必要な量を計算し、リスト化しましょう。
家族の人数×1日3食×3日分を目安にすると具体的な数量が見えてきます。
主食、たんぱく質源、副菜、飲料など、バランスよく揃えることも忘れずに。
賞味期限の見える化
備蓄品には購入日と賞味期限を書いたラベルを貼り、期限の早いものを手前に置くなどの工夫を。
100円ショップの収納ケースやファイルボックスなどを活用して、食品ごとに分類すれば管理も簡単です。
定期的に“食べて補充”=ローリングストック
例えば月に1度「備蓄点検日」を決め、期限が近い食品を普段の食事に取り入れましょう。
消費した分はすぐに補充。
これを習慣化すれば、無理なく備蓄が循環していきます。
よくある疑問とその答え(Q&A形式)

Q1. 賞味期限が切れたものはすぐ捨てるべき?
A1. 食品によっては「消費期限」と異なり、賞味期限を過ぎてもすぐに食べられなくなるわけではありません。
缶詰や乾物などは、保存状態が良ければ数ヶ月程度過ぎても問題ないケースも。
ただし、見た目や匂いに異変がある場合は食べないようにしましょう。
Q2. 賞味期限が近い食品のアレンジ方法は?
A2. レトルトカレーや缶詰のツナは、炊き込みご飯やパスタ、炒め物に応用できます。
おやつや非常食用のお菓子は、子どものおやつタイムやお出かけ用に回すと無駄がありません。
ポイントは“おいしいうちに楽しんで使う”ことです。
プチコラム|我が家の備蓄食品活用法

我が家では、毎月1日を「備蓄ごはんデー」として、備蓄食材だけで献立を組んでいます。
子どもたちと一緒に「この缶詰は何に使う?」と考える時間が、非常時の疑似体験にもなり、防災教育にもつながります。
ゲーム感覚で実践できるのが継続のコツです。
まとめ|少しずつ始めれば大丈夫
備蓄の賞味期限管理は難しいと思われがちですが、リスト化・見える化・ローリングストックという3つの工夫で、誰でも実践可能です。
「期限切れを出さない」ではなく「おいしいうちに食べて次を補充する」という意識で、無理なく備蓄を続けていきましょう。
まずは家にある食品の期限をチェックすることから始めてみてください。