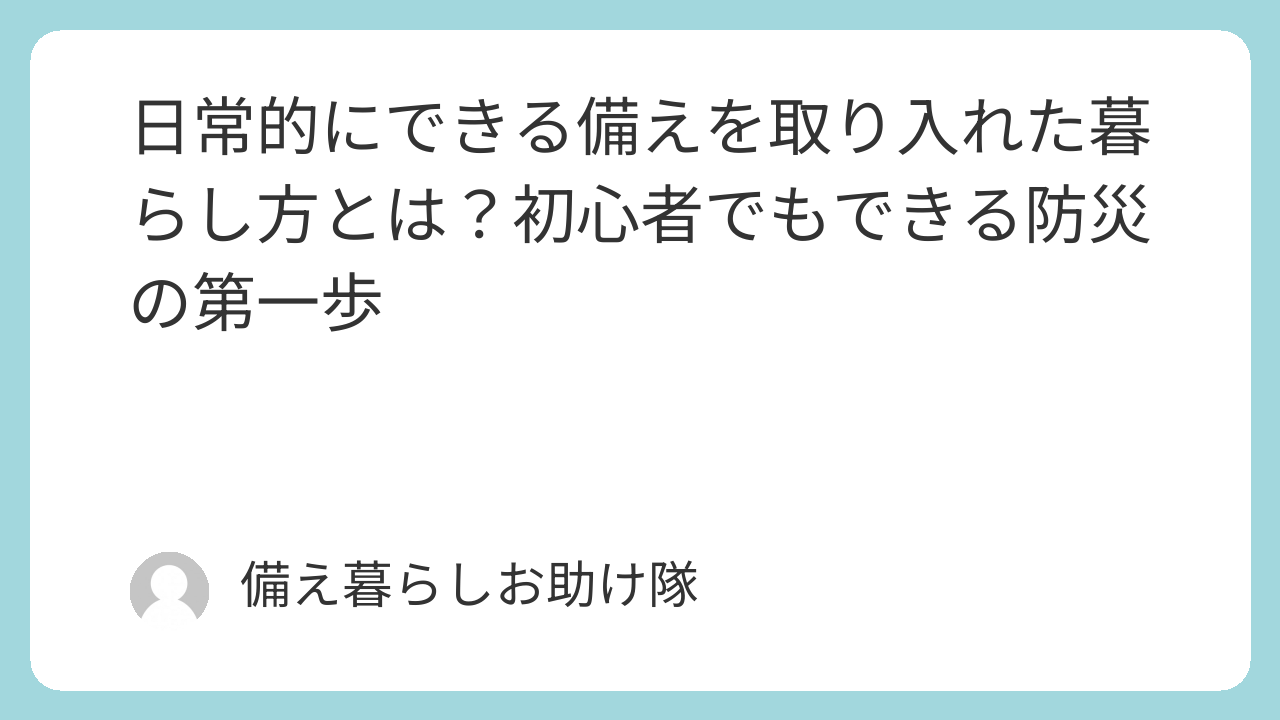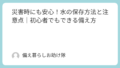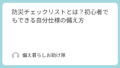なぜ備えが必要なのか
地震や台風などの自然災害、ライフラインの停止、突然のパンデミック——これらはいつ起きてもおかしくありません。
ニュースを見て「自分も何か備えないと…」と感じたことはありませんか?
でも、特別な装備や知識がないと難しそう…と構えてしまう方も多いはず。
実は、日常のちょっとした習慣の中にも「備え」は取り入れられるんです。
日常備蓄とは?|初心者向けにやさしく解説
日常備蓄とは、特別な防災グッズを買い込むのではなく、「いつもの生活用品を少し多めにストックしておく」という考え方。
例えば、飲料水やレトルト食品、トイレットペーパーなど、日頃から使っているものを、常に数日〜1週間分多めに用意しておくことで、非常時にも困らないという仕組みです。
この方法なら、わざわざ「防災用品」として準備するのではなく、普段の買い物の延長線上で始められます。
特に、買い物が頻繁にできない高齢者世帯や、育児中の家庭にもおすすめ。
実はこの方法、政府や自治体でも推奨されているんですよ。
実践パート|どうやって始める?どう選ぶ?
ステップ1:普段よく使うものをリストアップ
まずは、日常で必ず使っている食品や日用品を洗い出しましょう。
レトルトカレー、インスタント味噌汁、乾麺、缶詰、トイレットペーパー、歯磨き粉などが例です。
特に「使ったら必ず補充する」クセをつけることが重要です。
ステップ2:「ローリングストック」を実践
「ローリングストック」とは、ストックした食品や日用品を日常的に使いながら、常に一定量を保つ方法。
例えばレトルトカレーを6個用意し、1つ使ったらすぐに1つ補充する、というサイクルを繰り返します。
期限切れも防げて一石二鳥。
ステップ3:収納と記録で“見える化”
在庫管理ができるよう、収納場所を決めてラベルを貼る、賞味期限を記録しておくといった工夫も有効です。
スマホのメモアプリや冷蔵庫のホワイトボードなども活用して、「何がどれだけあるか」がわかる状態にしておきましょう。
よくある疑問とその答え(Q&A形式)
Q1. どれくらい備えればいいの?
A1. 基本は「最低3日分、できれば1週間分」が目安です。
家族の人数やペットの有無などによって調整してください。
例えば4人家族なら、飲料水だけでも2L×4人×3日=24L必要になります。
Q2. 買いすぎて結局使わなかったら?
A2. 普段から使っているものをストックするのがポイント。
非常食専門の高価なセットを大量購入するより、「普段食べるレトルトや缶詰」を多めに用意して、期限内に食べて補充するサイクルが現実的です。
プチコラム|「うちはこうしてます」日常備蓄のリアル
我が家では、月初めに「備蓄確認日」を設けています。
カレンダーにチェックを入れて、非常食や水、電池の数を家族で確認。
子どもたちも「今日はカレー食べて補充する日!」と楽しみにしています。
こうして家族みんなで関心を持つことが、備えの第一歩になるんです。
まとめ|少しずつ始めれば大丈夫
防災は「完璧を目指すこと」ではなく、「無理せず続けること」が大切。
最初からすべてを揃えようとせず、今あるものを少し多めに準備するだけで、立派な備えになります。
まずは、次の買い物でレトルト食品や水を1〜2個多めに買ってみましょう。
それがあなたと家族の安心に、確実につながっていきます。