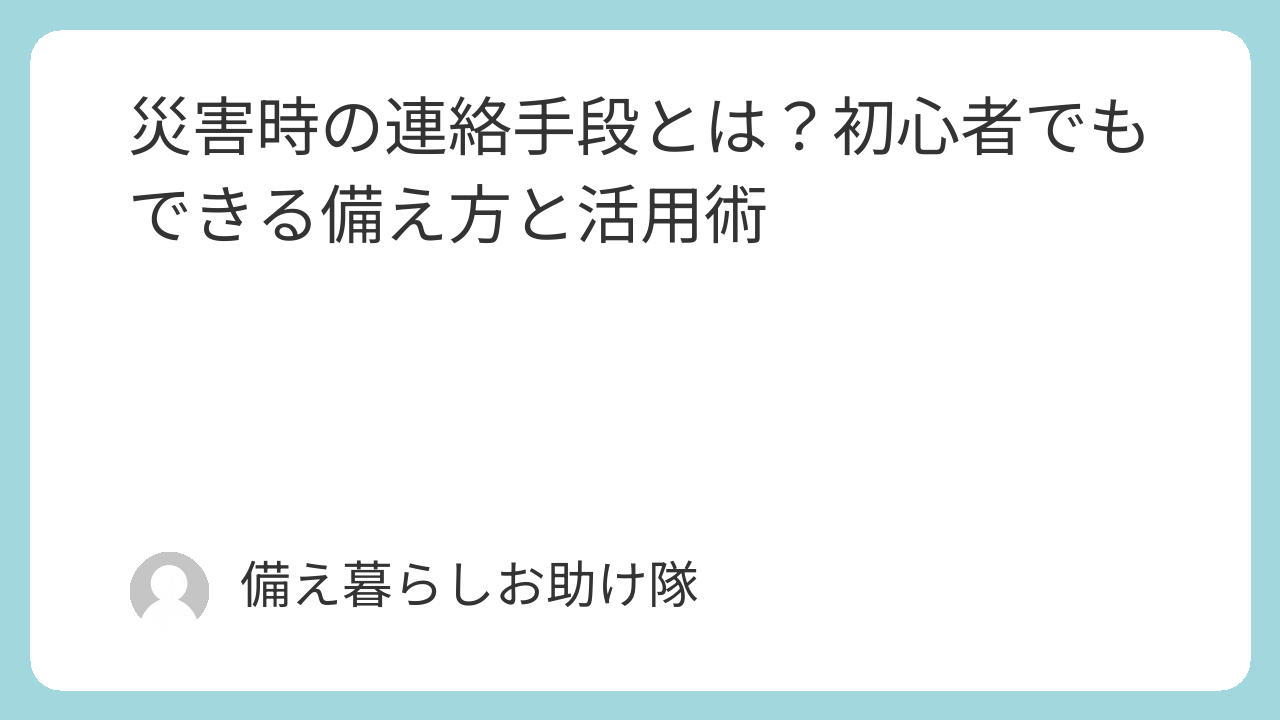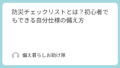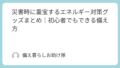なぜこの備えが必要なのか?
地震や豪雨など大規模災害が起きたとき、最も不安になるのが「家族と連絡が取れない」ことではないでしょうか。
実際、スマホがつながらない、電話がパンクするという事態はよく起こります。
でも、いくつかの準備をしておけば、災害時にも落ち着いて連絡を取り合える手段を確保できます。
災害時の連絡手段とは?|初心者向けにやさしく解説

災害時の連絡手段とは、停電や通信障害が起きても家族や関係者とつながるための方法やツールのことです。
一般的に、災害時は携帯電話の通信網が混雑し、通話やインターネットが使いづらくなります。
そのような状況でも活用できるのが「災害用伝言サービス」や「SNS」「トランシーバー」などの代替手段です。
実は、こうした手段を“知っているだけ”でも安心感が変わります。
緊急時に慌てないために、今のうちに仕組みや利用法を理解しておくことが大切です。
実践パート|どうやって始める?どう選ぶ?
STEP1|家族で“連絡ルール”を事前に決める
最も大事なのは「誰と、どこで、どうやって連絡を取るか」を災害前に決めておくことです。
- 安否確認は○○を通じて(例:母にLINE、兄に電話など)
- 家族間の集合場所や避難場所の再確認
- 「〇回以上連絡が取れなければ、○○に向かう」などのルールを設定
紙に書いて冷蔵庫などに貼っておくと、誰でもすぐ確認できます。
STEP2|災害時に使える通信手段を知っておく
災害時の連絡手段には以下のようなものがあります。
- 災害用伝言ダイヤル「171」(音声):家族間でのメッセージの録音・再生が可能
- 災害用伝言板(Web171/キャリア各社):スマホやPCで閲覧・登録できる
- SNS(X〈旧Twitter〉・LINEなど):インフラが生きていれば迅速な情報共有が可能
- 防災ラジオ・トランシーバー:電波障害時でも使える機器を1台持っておくと安心
- モバイルバッテリーやソーラー充電器もセットで準備を
STEP3|実際に“練習”しておく
家族で171の使い方を試してみたり、オフライン時でも使えるメッセージアプリを体験しておくことも効果的です。
毎年1回「防災週間(9月1日)」などのタイミングで見直すと、備えが習慣になります。
よくある疑問とその答え(Q&A形式)
Q1. 災害用伝言ダイヤルって、いつ使えるの?
A1. 災害発生時にNTTなどがサービスを開始します。
練習用期間も年数回あるので、事前に家族で試しておくと安心です。
Q2. スマホが圏外のときはどうするの?
A2. 圏外や電池切れに備えて、防災ラジオや手回し充電器、トランシーバーなどの“非ネット依存型”ツールを準備しましょう。
また、掲示板や避難所での伝言も想定して、筆記具とメモ帳を備えておくと役立ちます。
プチコラム|うちではこう備えています
我が家では、毎月1日に家族LINEグループに「連絡テスト」を送っています。
「生存確認」ではなく、「今月も元気だよ」という軽い内容にしておけば、習慣として続きます。
また、小学生の子どもとは「もし連絡が取れなかったら、○○公園で会う」と決めています。
小さな子でも覚えやすいルールを決めておくことが、親の安心にもつながっています。
まとめ|少しずつ始めれば大丈夫
通信は“命綱”とも言える大事な備え。
ですが、すべてを一度に完璧にそろえる必要はありません。
まずは災害伝言サービスを1つ使ってみるだけでもOK。
家族で話し合い、ルールを決めるだけで、大きな一歩になります。
今日からできる備えを1つ、ぜひ始めてみましょう。