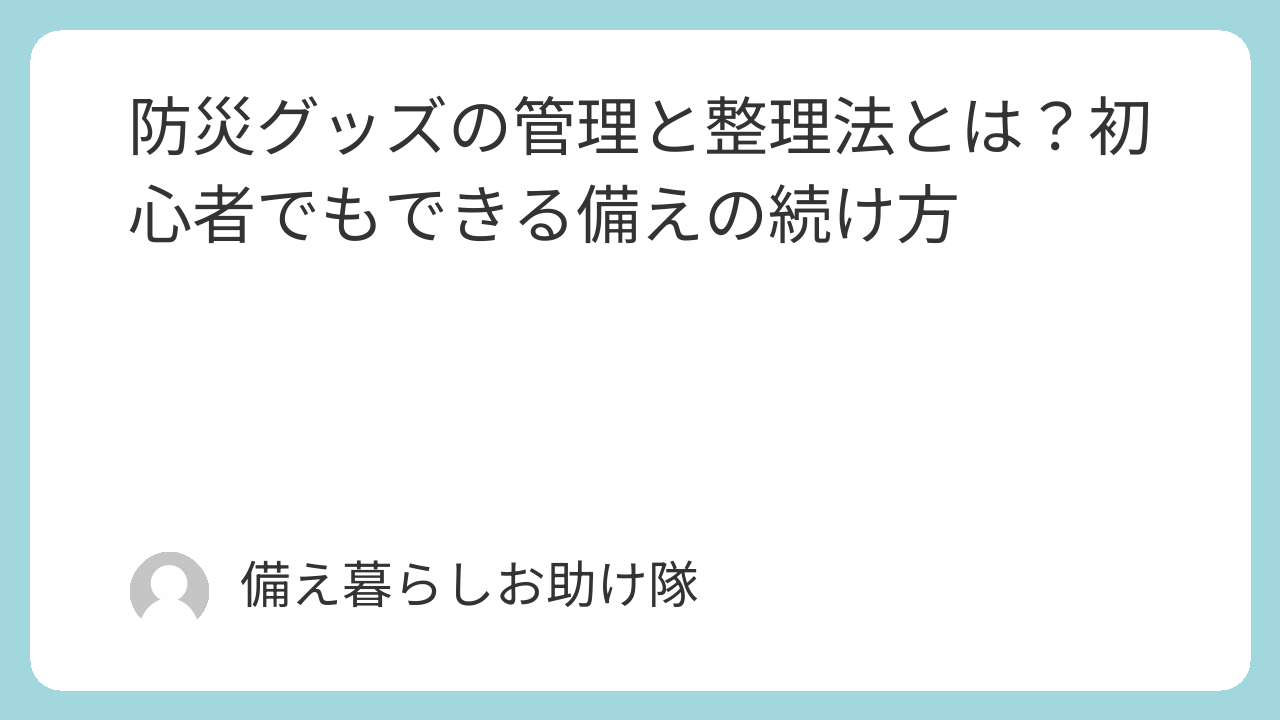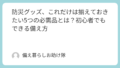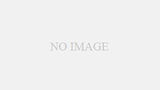なぜこの備えが必要なのか?
地震や台風などの災害が頻発する日本では、防災グッズを備えておくことが重要です。
しかし、「買っただけで満足してしまった」「どこに何があるか分からない」という人も多いのではないでしょうか。
実は、管理と整理こそが“いざという時に使える備え”の第一歩。
実践しやすい方法で、今日から始められます。
防災グッズの管理と整理とは?|初心者向けにやさしく解説
防災グッズの「管理と整理」とは、必要な物を正しくそろえ、見つけやすく、使いやすく保管しておくことを指します。
非常時は数秒〜数分の行動が命を左右するため、どこに何があるかを即座に把握できるかどうかが重要です。
また、防災グッズは食料・水・衛生用品・照明など多岐にわたり、定期的な点検や賞味期限の管理が必要です。
「買ってそのまま」「袋に詰めて終わり」では、本番に使えない可能性が高くなります。
実は、整理整頓が苦手な人でも、少しの工夫とルール化で無理なく続けられるようになります。
実践パート|どうやって始める?どう選ぶ?
STEP1|“3分類ルール”でグッズを分ける
防災グッズは「すぐ持ち出す用」「自宅待機用」「日常兼用」の3つに分類するのが基本です。
- ① 非常持ち出し袋:災害発生直後にすぐ持って避難する物(1次避難用)
- ② 自宅備蓄用:避難せず家に留まる際に使う物(2次避難用)
- ③ 日常兼用型:日常でも使いながら、非常時にも役立つ物(ローリングストックなど)
分類することで、用途に応じた管理がしやすくなります。
STEP2|収納場所を固定し、家族で共有する
「どこに何があるか分からない」は非常時の大敵。
収納場所は以下のように決めておくのがおすすめです。
- 持ち出し袋:玄関・リビングなど“すぐ手に取れる場所”に
- 自宅用備蓄:パントリーやクローゼットの一角に「災害棚」を作る
- 日常兼用:使ったら元に戻すクセを家族で共有
子どもや高齢の家族とも定期的に確認しておくことで、家族全員の防災力がアップします。
STEP3|“年2回の点検日”を決めて見直す
防災グッズの最大の落とし穴が「劣化や賞味期限切れ」。
これを防ぐには、定期的な見直しが必要です。
おすすめは「防災の日(9月1日)」と「年末年始」の2回。
点検リストを作っておけば、10分程度で済みます。
食品・水・電池・充電器・医薬品などのチェックは忘れずに!
よくある疑問とその答え(Q&A形式)
Q1. どれくらいの量の防災グッズを持っておけばいいの?
A1. 一般的には「最低3日分」が目安。可能なら「7日分」あると安心です。
特に水は1人1日3リットルが必要と言われています。
Q2. 片づけが苦手で管理が続きません…
A2. まずは100円ショップのボックスやラベルを活用して、“見える化”から始めましょう。
定位置管理をすれば、片づけもラクになります。
「最低限だけ用意する」「使ったら補充する」の習慣もポイントです。
プチコラム|うちではこう備えています
我が家では、防災グッズの管理に「スマホメモアプリ」を使っています。
リスト化しておけば、出先でも確認できて便利です。
また、子どもと一緒に“防災宝探し”を開催し、グッズの場所を一緒に確認。
ゲーム感覚で取り組むことで、家族全員が自然と場所を覚えられました。
防災は“暮らしの一部”として楽しみながら取り組むことが、続けるコツです。
まとめ|少しずつ始めれば大丈夫
防災グッズの管理と整理は、難しく感じるかもしれません。
でも、まずは「場所を決める」「見えるようにする」だけでも十分な備えになります。
完璧を目指さず、“できることから一歩ずつ”が大切です。
今日、防災袋の中身を1つチェックする。
それだけでも立派な防災です。